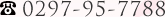生ゴミ処理機の方式
生ゴミ処理機の種類と特徴
- 「自然還元システム「TRASH」(トラッシュ)」
場所さえあれば、この方法はある程度理想に近いと思われる。敷地さえあればランニングコストもかからず、寿命も半永久的である。 - 「バイオ処理機(堆肥型)」
バイオを使って、生ゴミを攪拌しながら分解する方法であるが、炭化式に比べてランニングコストは少なくて済む。しかし、日常の手入れ等に多少のコツを要する。完全な状態で使うと臭いも少なく便利であるが、良質の堆肥は作りにくいので、問題になっている所もある。 - 「炭化乾燥型処理機」
これは電気・ガス等で高温にし、乾燥半炭化して容積を減らし処理する方法である。地球温暖化などの問題はあるが、機械の大きさ等コンパクトである。ランニングコストもかかるという欠点もある。 - 完全消滅型生ゴミ処理機物理的に不可能、生ゴミが消滅するということは考えられない。
国の循環型社会計画案
| 循環型社会計画案 | 循環型社会形成推進基本 | 食品リサイクル法 | 焼却炉規制 |
循環型社会を形成「10年度にごみ処分量半減」
リサイクル促進とごみの発生抑制を目指す、国の2010年度までの循環型社会形成。推進基本計画案が22日、明らかになった。10年度のごみ処分量を2000年度の約半分の2700万トンとし、国民と企業の意識改善目標も定めている。27日の中央環境審議会に提出、3月末までに閣議決定し、03年度から実施する。循環型社会形成推進基本法に基づく初の計画で、5年後に見直す予定だ。
計画案は大量生産と大量消費の社会は持続不可能とし、資源を循環させ自然と共生する社会を提案。四季を感じながら生きるスローライフが受け入れられ、生ごみの堆肥利用などが進むとイメージを示した。10年度の具体的数値目標として、リサイクル推進と資源消費量の抑制で、廃棄物の最終処分量を2000年度(5600万トン)の約半分の2700万トンと設定。国民一人ひとりの意識改善が不可欠とし、ごみの減量化やリサイクルを心がけている人の割合を90%(01年の内閣府調査で71%)、環境保全活動に参加した人の割合を50%(02年の環境省調査で20%)にすることを目指すとした。企業に対しても環境対策と成果を会計的に示す環境会計の積極導入を呼び掛けることにした。
| 年度 | 2000年 | 2010年 | |
| 資源生産性(1トン当り) | 28万円 | 39万円 | |
| 循環利用率 | 10% | 14% | |
| 最終処分量 | 5600万トン | 2700万トン | |
| 国民 | ゴミの減量化を心がけている | 71% | 90% |
| グリーン購入している | 83%(01年7月) | 90% | |
| 環境保全活動に参加した | 20%(02年2-3月) | 50% | |
| 上場企業 | グリーン購入実施 | 15%(01年度) | 50% |
| 環境会計実施 | 23%(01年度) | 50% | |
多孔質で微生物の繁殖に好都合
毎日のようにゴミ回収車が忙しく走り回る時代である。何とかゴミを少なくしたい、そんな考えから生まれたのが生ゴミ分解装置だろう。この装置で生ゴミを分解し、減量する主役は微生物だが、その微生物を繁殖させる
のに、おがくずや木材チップは有効である。
金属やプラスチックと違って、おがくずや木材チップは多孔質であるために、湿度を適度に保ち、逆に水はけも良く過度に湿らず、通気性もよいので、空気との接触で繁殖する妖気性バクテリアなどの微生物にとって、繁殖に好都合な場所となる。
微生物は生ゴミを栄養源として分解し、最終的には二酸化炭素と水にする。実際には装置の中に、おがくずと生ゴミを入れ、分解を早めるために好気性微生物を入れ、空気との接触を多くするために自動撹拝するといった操作をする。微生物を加えずに、生ゴミ中の微生物を利用することもある。 おがくずを利用した生ゴミ分解装置では悪臭が発生せず、生ゴミに含まれていたカリ、リン、窒素などが、おがくずに含まれるようになるので、生ゴミ処理後の、おがくずは、肥料や土壌改良材として有効であり、また、キノコ栽培用の培地としての利用も可能である。
おがくずよりも、サイズの大きい木材チップを使用した例も報告されている。この場合には、生ゴミ処理によってチップの大きさが小さくなるものの、おがくず同様、ミネラル類の濃度の増加がみられる。チップの場合には、おがくずのように細かくないので、たい肥化は難しいようだが、その形状を利用して、ボードなどへの利用可能性も検討されている。生ゴミ処理中に微生物の働きで、固かったチップが軟らかくなっているので、蒸気をあてて軟らかくする工程が省略でき、生ゴミ処理チップのままで、加熱、圧密化処理することで接着剤なしにボード製造が可能であるという。処理チップでは、微生物によって物理的な劣化も起こっているために、比較的低いエネルギーで粉体化が可能であり、たい肥やキノコ培地としての利用も可能である。
生ゴミ分解装置による生ゴミ分解は、微生物という自然の力と、おがくずなどの廃材を効率よく利用した環境にやさしい処理法といえよう。
(東京大学大学院農学生命科学研究科教授・谷田貝光克)
参考文献(生ゴミ処理の基礎知識)
| はじめに | 処理方式 | 分解の原理 | 装置の分類 | 性能指標 |
| 操作条件 | 臭気対策 | 諸問題 | おわりに |
はじめに
「はじめに-生ゴミ処理装置開発の意義-」 静岡大学工学部物質工学科 松 田 智
※本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。
最近、各種の生ゴミ処理機が多数開発されるようになった。
その背景にはゴミ問題の深刻化がある。家庭・オフィスなどから排出される一般廃棄物は、90年代を通じてほぼ年間5000万トンで推移している。一般廃棄物はリサイクル率が約1割と低く、大半が焼却されている。その焼却灰を埋め立てる最終処分場の枯渇が現実の問題になってきたことと、焼却に伴って発生するダイオキシンが問題となって、焼却すべきゴミの量そのものを減らす必要が以前よりさらに強まった。一般廃棄物の大部分は可燃ゴミであり、可燃ゴミの約4割が生ゴミと言われている。 したがって、生ゴミを一般廃棄物から除去できれば、それだけで焼却すべきゴミの量がかなり減少する。 生ゴミ中の塩分はダイオキシン発生の一因でもあるから、この面でも生ゴミの隔離には意味がある。
さらに、一般廃棄物に生ゴミを混入させなければ、残りは紙・繊維・プラスチック・ガラス・金属等であるから、悪臭やハエ等の発生もなく、機械的分別による再資源化の可能性が高まる。 焼却処分する場合にも、廃棄物中の水分が減少して効率的な熱回収が行える。こうして見ると、一般廃棄物中に生ゴミを混入させないことによるメリットは、極めて大きい。たとえ生ゴミをコンポスト化して土壌還元することが可能でない場合にも、発生源で生ゴミを処理することの意義は大きい。この点は大いに強調したい。
生ゴミは腐敗しやすく悪臭も放ちやすいので、輸送や集積が難しい。しかも発生源が分散している。当然、各発生源での個別処理が望ましい。ディスポーザーを用いて生ゴミをし尿や雑排水と一括して処理する方式は、最近米国などで普及しつつあり、ユーザーから見れば確かに手間の省ける魅力的な方式である。しかし浄化槽への負荷が大きくなり、余剰汚泥の発生量も当然増える上に、万一トラブルが発生した場合には、ユーザーにはまったく手に負えない事態となる。
やはり、生ゴミは生ゴミ単独で処理する方式が、廃棄物処理上のセキュリティの面でも望ましいと言えるであろう。 以上のように見てくると、家庭用・業務用生ゴミ処理機の開発は、社会的意義の非常に大きなものであり、単なるブームに終わらないだけの必然性を備えていると考えられる。
農水省が「食品廃棄物再商品化法案(仮称)」を国会に提出する方針を固めたことが、最近報道された。これは、外食産業や食品メーカーが出す生ゴミや残飯のリサイクルを促進しようとするもので、一定割合以上の生ゴミを肥料や家畜飼料にするよう義務づけることを目指している。したがって、家庭用だけでなく、今後、やや大型の、業務用の生ゴミ処理機の需要も高まって行くであろう。ただし後述するが、やや専門的な装置工学的に見た場合、特に小型の生ゴミ処理装置は、設計・操作の上で種々の難しい課題を抱えた、なかなかの難物である。